پل2025”N1Œژ3“ْپâ
ںùگخ‚ج“¹‚ً•à‚پ@3‰ٌ–ع
‘گ–ى‚©‚ç’ا•ھ‚ض
پ@ پ@پ@پ@پ@پ@‰ؤ–عںùگخ‚ھŒF–{‚ج‘وŒـچ‚“™ٹwچZ‚ج‹³ژِ‚¾‚ء‚½ژپA‹v—¯•ؤ‚ج—Fگl‚ئ‚ئ‚à‚ةŒنˆن‚©‚çچ‚—اژR‚ة“o‚èژ¨”[ژR’n‚ً
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@”گSژR‚ـ‚إ•à‚«”گSŒِ‰€‚ة‰؛‚è‚ؤ‚¢‚éپB‚»‚جژ‰r‚ٌ‚¾”o‹ه‚ج‚¢‚‚آ‚©‚ھ‹ه”è‚ةچڈ‚ـ‚ê“oژRکH‚ة‚ ‚è‚»‚ê‚ً
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@–K‚ث‚ؤ•à‚¢‚ؤ‚«‚ـ‚µ‚½پBچ،‰ٌ‚إ3‰ٌ–ع‚جںùگخ‚ج“¹‚إ‚·پA1‰ٌ–ع‚حںùگخ‚ج•à‚¢‚½ƒRپ[ƒX‚ًچ‚—اژR‚©‚ç”گSژR‚ض
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@•à‚«‚ـ‚µ‚½‚ھ‚¸‚ء‚ئ“o‚è‚إ‚«‚آ‚©‚ء‚½‚ج‚إ2‰ٌ–ع‚©‚ç‚ح”گSژR‚©‚ç‚ة‚µ‚ـ‚µ‚½پB
پ@پ@پ@پ@پ@’·–هگخ(6:26)پپƒoƒXپپJR‹v—¯•ؤ(7:00)پپ(7:21)‘گ–ىپ|(7:40)”گSŒِ‰€پ|(8:14)ژOچ‡–عپ|(8:32)‘ گصپ|(9:18)”گSژR
پ@پ@پ@پ@پ@پ|(9:43)”’ژRپ|ƒOƒ‰ƒCƒ_پ[ژR(9:54)پ—پ@پ|(10:25)–‘Œ`ژRپ|(10:38)ژ¨”[•½پ|(11:19)ژ‡‰_‘نپ|(11:43)ژ¨”[ژRپ|
پ@پ@پ@پ@پ@(12:44)چ‚—اژRپ|(12:54)”ٍ‰_‘نپ|(13:05)گ™‚جڈéپ|(13:17)چ‚—ا‘هژذپ|(13:40)‰¤ژq‹{پ|(13:59)’ا•ھ(14:04)پپƒoƒXپپ
پ@پ@پ@پ@پ@گ¼“S‹v—¯•ؤڈو‚èٹ·‚¦پپ(14:44)’·–هگخ |
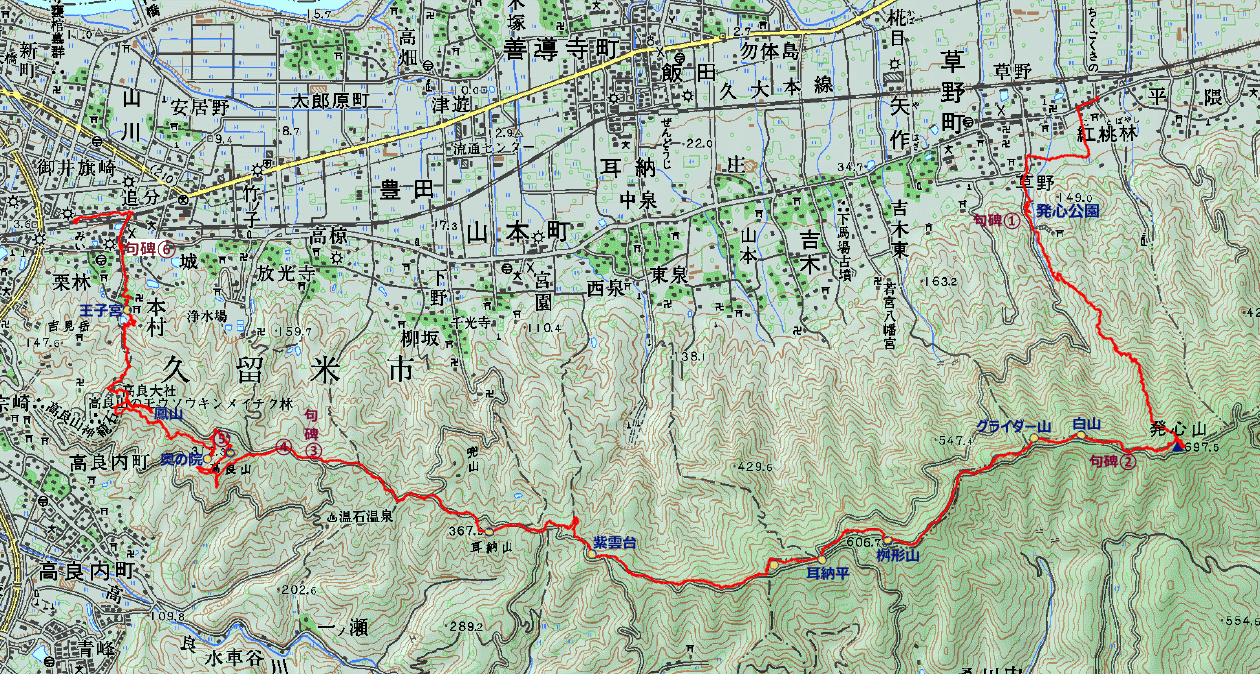 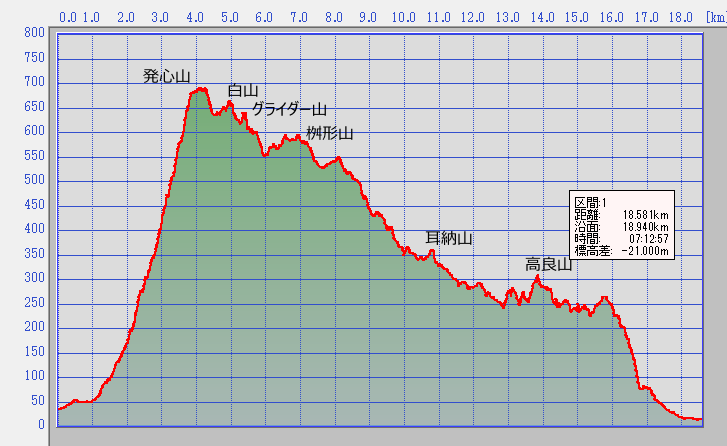 |
|
 
چ¶ JR‹v—¯•ؤ‰w‚إ
پ@پ@ˆأ‚¢‚¤‚؟‚ةڈو‚é
پ@“r’†‚إ–é–¾‚¯‚ئ‚ب‚é
‰E ‘گ–ى‰w
پ@پ@ICƒJپ[ƒh‚ھژg‚¦
پ@‚ب‚¢‚½‚ك‹v—¯•ؤ‰w‚إ
پ@گط•„‚ً”ƒ‚ء‚½پB
|
 
چ¶ ٹ`”¨‚ًŒ©‚ب‚ھ‚ç
پ@•à‚پA‘ڑ‚ھچ~‚èٹ¦‚¢
‰E ”گSŒِ‰€
پ@پ@چ÷‚ج–¼ڈٹ‚¾‚ھ
پ@•—‚ھ—₽‚¢پAƒgƒCƒŒ
پ@‚حگ…‚ھ‚إ‚¸ژg—p•s”\ |
 
چ¶ ںùگخ‹ه”è‡T
پ@پuڈ¼‚ً‚à‚ؤ
پ@پ@پ@ˆح‚ذ‚µ
پ@پ@پ@پ@’J‚جچ÷‚©‚بپv
پ@پ@‰ؤ–عںùگخ‚حŒF–{‚ج
پ@‘وŒـچ‚“™ٹwچZ‚ج‹³ژِ
پ@ژ‘م¤‹v—¯•ؤ‚جگe—F
پ@‚ً–K‚ثژ¨”[ژR‚ً•à‚«
پ@”o‹ه‚ًژc‚µ‚ؤ‚¢‚éپB
‰E گ…ٹQ‚إ“oژR“¹‚ھ
پ@•ِ—ژپBگخ•§‚ض‚ح
پ@‚¢‚¯‚ب‚¢پB |
 
چ¶ گV‚µ‚¢“oژR“¹“üŒû
پ@—ر“¹‚©‚ç“ü‚éپB
‰E ‚‚ع‚ٌ‚¾
پ@پ@‹}چâ‚ً“o‚éپB
پ@پ@پ@‚·‚茸‚ء‚½
پ@پ@گخ‚ھ—ًژj‚ً
پ@پ@ژأ‚خ‚¹‚éپB |
 
چ¶ ژOچ‡–ع
پ@‚±‚±‚ـ‚إ‚à‹}چâ
‰E ‘ گصپA‚±‚±‚©‚ç‚à
پ@‹}چâ‚ھ‘±‚پB
پ@ |
 
چ¶ ڈéڑ¬‚ج–k’[‚ة“’…
پ@ڈéڑ¬‚حƒJƒ„‚ھ
پ@ٹ ‚è•¥‚ي‚ê‚ؤ‚¢‚½پB
‰E ’}Œم•½–ى‚ً–]‚ق‚ھ
پ@‰à‚ٌ‚إƒ{ƒ“ƒ„ƒٹپB
|
 
چ¶ ”گSژR697.6m
پ@پ@ژOٹp“_‚ھ‚ ‚è
پ@‘گ–ىژپ‚جڈˆ“_‚إ
پ@1577”N’zڈ邵‚½‚ھ
پ@1588”N‚ة‚ح–إ‚ٌ‚إ
پ@‚¢‚éپB
‰E ”’ژR‚ً–]‚قپB |
 
چ¶ ˆئ•”‚ة‹ه”è‡U‚ھ
پ@پu”Z‚©‚ة
پ@پ@–يگ¶‚ج‰_‚ج
پ@پ@پ@—¬‚ꂯ‚èپvپ@
‰E ”°چج’n‚ًچ¶‚ة
پ@پ@Œ©‚ب‚ھ‚çچs‚پB |
 
چ¶ ”’ژR677m
پ@پ@“W–]‚ح‚ب‚¢‚ھپA
پ@ک[‚©‚ç‚جژR—e‚ھ
پ@—ا‚¢پB
‰E ƒOƒ‰ƒCƒ_پ[ژR‚ض
پ@پ@“Œ‘¤‚©‚ç‚ح
پ@پ@—V•à“¹‚ھ‚ ‚éپB
|
 
چ¶ ƒOƒ‰ƒCƒ_پ[ژR
پ@پ@“ْ–{گV‹Lک^ژ÷—§
پ@‹L”O”èپB
گVڈtƒtƒ‰ƒCƒg‚جگl‚à
پ@“oژRژز‚à‚¢‚ب‚©‚ء‚½
‰E ‹v—¯•ؤژsٹX
پ@پ@’}ŒمگىپA‰à‚ٌ‚إ
پ@ƒ{ƒ“ƒ„ƒٹپB |
 
چ¶ O‹´
پ@’تڈج گ½‹´
‰E –‘Œ`ژR
پ@پ@پ@606.5m
پ@پ@“W–]‚ح‚ب‚¢‚ھ
پ@ژOٹp“_‚ھ‚ ‚éپB
پ@پ@ |
 
چ¶ ژ¨”[•½
پ@چ،“ْ‚ح‚¾‚ê‚à
پ@‚¢‚ب‚©‚ء‚½پB
‰E ژ¨”[ƒXƒJƒCƒ‰ƒCƒ“
پ@‚ھژ©‰q‘à‚ة‚و‚ء‚ؤ
پ@‘¢‚ç‚ꂽ‚±‚ئ‚ھ
پ@ڈ‘‚¢‚ؤ‚ ‚éپB
|
 
چ¶ ’·ٹâژR•ھٹٍ
پ@چ‚—ا‘هژذ‚ـ‚إ‚ـ‚¾
پ@6‚‹‚چ‚ ‚éپB
‰E —½‰_‘ن
پ@ژ¨”[ƒXƒJƒCƒ‰ƒCƒ“
پ@‚ة‚ح‚ظ‚©‚ةگگ‰_‘ن
پ@ژ‡‰_‘نپA”ٍ‰_‘ن‚ھ
پ@‚ ‚éپB |
 
چ¶ ژ‡‰_‘ن
پ@‘O‰ٌ‚ح‚â‚ش‚ج’†
پ@‚¾‚ء‚½‚ھٹ ‚è•¥‚ي‚ê
پ@‚ؤ‚¢‚½پB
پ@
‰E ژ‡‰_‘ن”è
پ@ژ¨”[ژRژY‹ئٹJ”“¹
پ@ڈ؛کa38”N¥¥¥¥
پ@—¤ڈمژ©‰q‘॥¥‚ج
پ@•¶ژڑ‚ھ‚©‚낤‚¶‚ؤ
پ@“ا‚ك‚½پB
پ@پ@ |
 
چ¶ ژ¨”[ژR‚ض
‰E ژ¨”[ژR368‚چ |
 
چ¶ ٹ•ژR•ھٹٍ
پ@چ،‰ٌ‚حƒpƒX
پ@
پ@پ@
‰E ںùگخ‹ه”è‡V
پ@پ@پu’}ŒمکH‚â
پ@پ@پ@ٹغ‚¢ژRگپ‚
پ@پ@پ@پ@ڈt‚ج•—پv
پ@پ@‹ه‚ة‚؟‚ب‚ٌ‚إ
پ@ٹغ‚¢Œٹ‚ھٹJ‚¢‚ؤ
پ@‚¢‚½پB |
 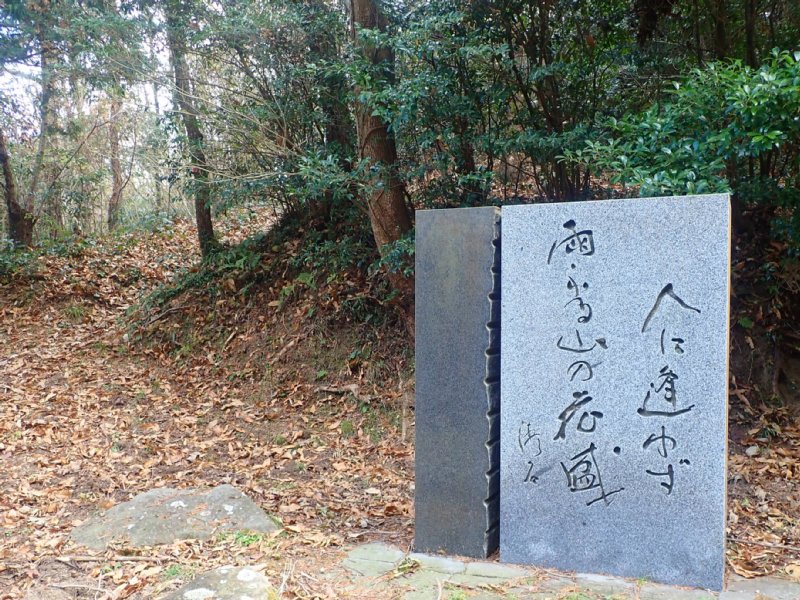
چ¶ ‚‚ت‚¬—ر
پ@پ@‚±‚جژR‚إ‚ح
پ@‚ك‚¸‚炵‚¢
پ@—ژ—tژ÷پA‹ك‚‚إ
پ@’إ‘ù‚ھچح”|‚³‚ê‚ؤ
پ@‚¢‚½پB
‰E ںùگخ‹ه”è‡W
پ@پ@پuگl‚ةˆ§‚ي‚¸
پ@پ@پ@پ@‰J‚س‚éژR‚ج
پ@پ@پ@پ@پ@‰شگ·‚èپv
پ@‚±‚±‚ـ‚إ’N‚ة‚à
پ@‰ï‚ي‚ب‚©‚ء‚½پB |
 
چ¶ چ‚—اژR‚ض
‰E چ‚—اژR 312m
پ@پ@ژR’¸‚©‚ç‚ج
پ@“W–]‚ح‚ب‚¢پB
|
 
چ¶ چ‚—اژR‚©‚ç–]‚ق
پ@•َ–ژR•û–ت
‰E •à‚¢‚ؤ‚«‚½
پ@”گSژR‚©‚ç‚ج—إگü
|
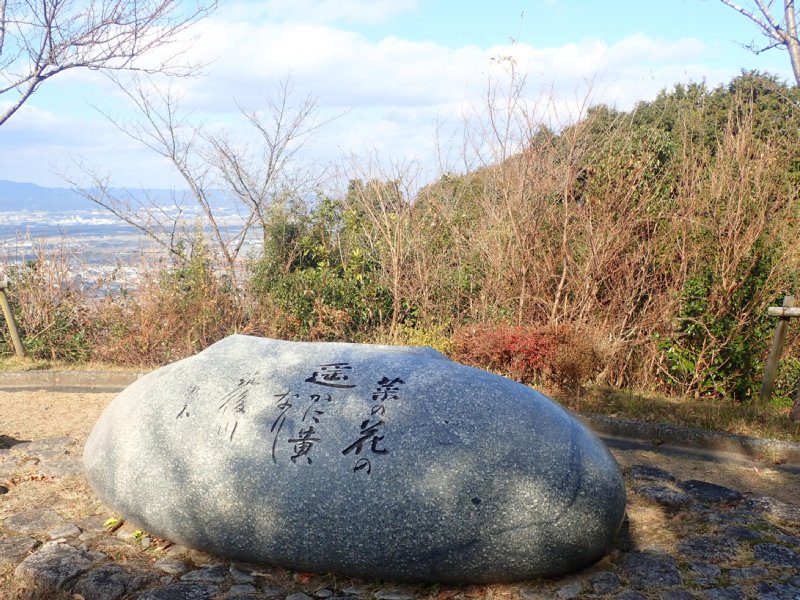 
چ¶ ںùگخ‹ه”è‡X
پ@پuچط‚ج‰ش‚ج
پ@پ@‚ح‚é‚©‚ة‰©‚ب‚è
پ@پ@پ@’}Œمگىپv
‰E ”ٍ‰_‘ن‚ة‚ ‚éپB
|
 
چ¶ چ‚—ا‘هژذ
پ@پ@’}Œمچ‘ˆê‚ج‹{
پ@چ‚—ا‹تگ‚–½‚ًâJ‚è
پ@1600”Nˆبڈم‚ج—ًژj‚ً
پ@ژ‚آ‚ئ‚¢‚¤پB
‰E گ³Œژ‚ئ
پ@‚ ‚ء‚ؤژQ”qژز‚à
پ@‘½‚©‚ء‚½پB
پ@
پ@ |
 
چ¶ ’ا•ھ‚ة‰؛‚é
‰E ‹GگكٹO‚ê‚ج
پ@ƒVƒƒƒNƒiƒQ‚ج‰ش‚ھ
پ@“ٌ—ض
|
 
چ¶ 400’iˆبڈم‚جگخ’iپAپ@پ@—¼کe‚ة‚ح
پ@ƒVƒƒƒNƒiƒQ‚âچ÷‚ھ
پ@گA‚ي‚ء‚ؤ‚¢‚½پB
‰E “®—گ–I‚جƒ„ƒOƒ‰
پ@“®—گ–I
پ@پ@‰¤ژqژل‹{”ھ”¦‹{‚ج
پ@ژپژq‚½‚؟‚ھ‘إڈم‚°‚é
پ@‰ش‰خپA–ˆ”N9Œژ15“ْ‚ة
پ@ٹJچأ‚³‚ê‚éپB
|
 
چ¶ ‰¤ژq’rپ@پv
‰E ‰¤ژq‹{
پ@چ‚—اŒنژqگ_ژذ
پ@چ‚—ا‹تگ‚–½‚جچcژq
پ@‹مگl‚ًâJ‚éگ_ژذپ@ |
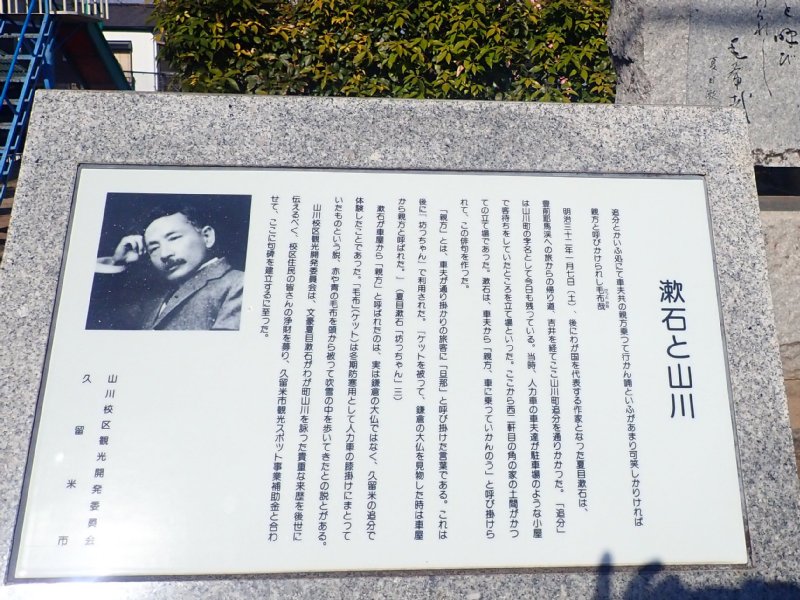 
پ@ںùگخ‹ه”è‡Y
پ@پuگe•û‚ئ
پ@پ@Œؤ‚ر‚©‚¯‚ç‚ꂵ
پ@پ@پ@–ر•zچئ
پ@پ@پiƒPƒbƒg‚©‚بپj
پ@–¾ژ،32”N1Œژ7“ْ
پ@‰ؤ–عںùگخ‚ح–ë”nŒk
پ@‚©‚ç‚ج—·‚ج‹A‚蓹
پ@‚±‚±‚إگl—حژش‚ً
پ@‚·‚·‚ك‚ç‚ꂽ‚ئ
پ@‚¢‚¤پB |