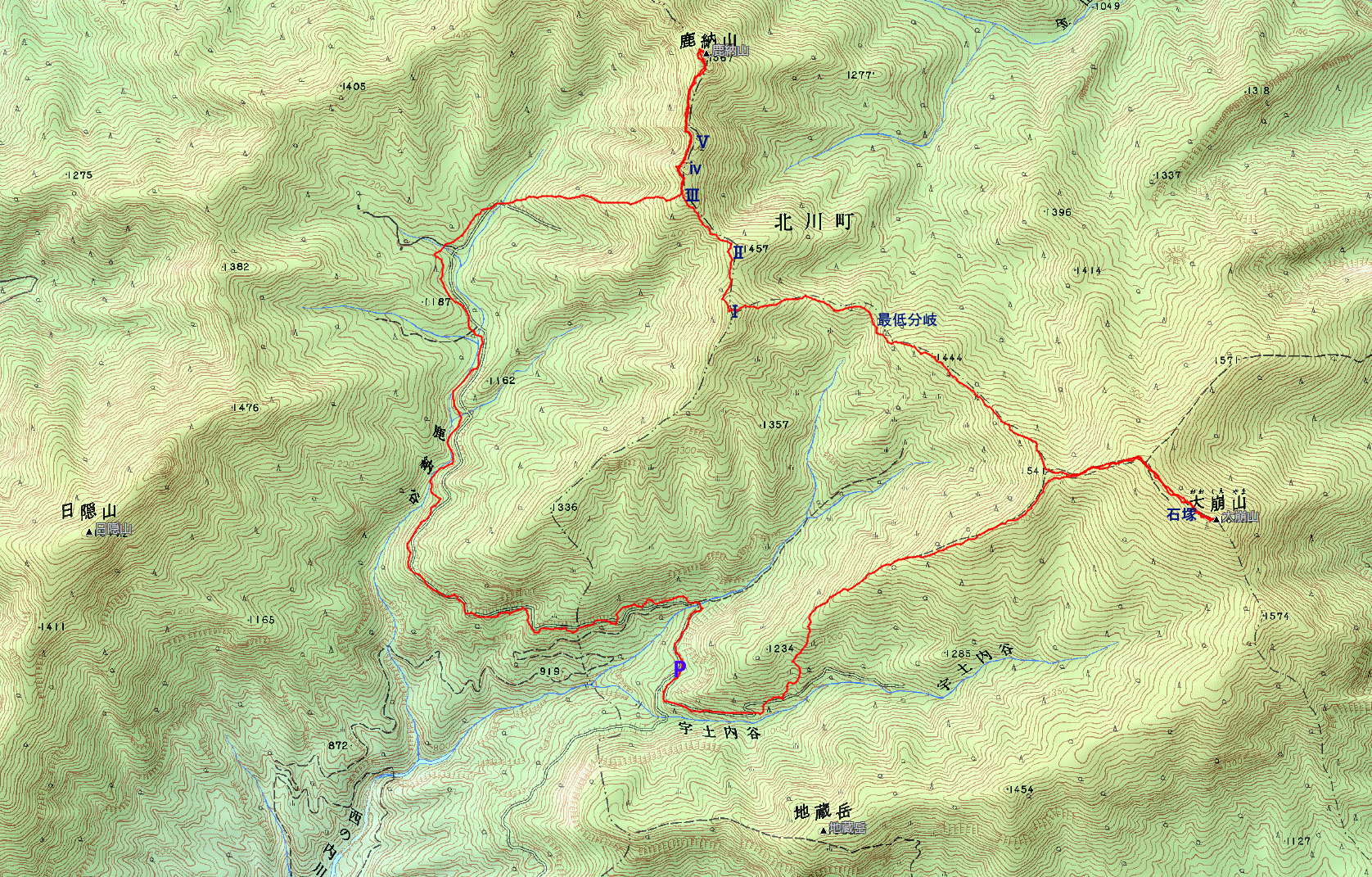 ≪2025年4月26日≫
宇土内谷から大崩山、鹿納山周回 ≪2025年4月26日≫
宇土内谷から大崩山、鹿納山周回
4年ぶりの大崩山-鹿納山周回、今回はスパルタ山行をうたうミッチン塾の主催、後期高齢者、アラエイティ
年々落ちてゆく体力に不安もありましたが何とか歩きとおせました。稜線上のアケボノツツジはまだ蕾でしたが
1300mあたりは見頃を迎えていました。雲一つない青空に展望も素晴らしく、鹿納坊主山頂からの360度の展望は
感動ものでした。
日之影温泉車中泊=青雲橋(5:00)=上鹿川(6:00)=(6:50)宇土内登山道入口(7:00)−(7:45)尾根−(8:45)鹿納分岐−
(8:57)祝子川分岐−(9:06)大崩山山頂(9:23)−(9:43)鹿納分岐分岐−(10:10)1444mP−(10:32)最低鞍部−
(10:50)ピーク−(11:24)分岐−
(11:50)権七谷分岐−(12:00上)昼食(12:45)−(12:21)鹿納山(13:12)−(13:52)分岐
− (14:38)鹿納谷登山口−(15:55)駐車地点(16:07)=(16:40)上鹿川=(17:28)星雲橋=(18:26)道の駅通潤橋(18:42)=(20:06)自宅 |
 |
| 頭上を覆うアケボノツツジ |
|
 
左 大崩山登山口入口
ここまでの林道は
伐採中のことも
あって荒れては
いませんでした。
右 登山口
林道から登山道へ |
 
左 登山道は作業道で
寸断、伐採後植林
された中を登る。
右 ブナの尾根に出る。
|
 
左 アケボノツツジが
お出迎え。
右 アケボノツツジに
笑顔がこぼれる。 |
 
左 見ごたえ十分
右 目的の鹿納坊主を
望む
|
 
左 花越しに鹿納坊主
右 馬酔木の中を行く |
 
左 祝子川
登山口分岐
右 大崩山山頂
一等三角点
「祝子川山」
ミッチン塾の
旗開き。
|
 
左 分岐から右へ
鹿納山へ
右 かってあった
スズタケは枯れ
どこでも歩ける。
|
 
左 釣鐘山を望む。
右 めざす鹿納坊主
|
 
左 大崩山、中和久、
上和久、七日廻岩
右 まだまだ下りが
続く。
|
 
左 下った道を
振り返る。
右 馬酔木の中を
登り返す。 |
 
左 頭上の
アケボノツツジ
右 アケボノツツジと
傾山
|
 
左 ピークまで登り
返し、尾根を行く
右 釣鐘山、日隠山
|
 
左 鹿納谷分岐
帰りはここから下る
右 めざす鹿納坊主
尾根を行く仲間
|
 
左 アケボノツツジの
蕾はかたかったが
ミツバツツジが
見ごろ
右 めざす鹿納山
|
 
左 下ってきた尾根
右 権七谷分岐
広場となっていて
幕営場所となって
いる。
かってはササヤブの
なかだった。
権七谷分岐2006
|
 
左 鹿納坊主を前に
昼食休憩
右 鹿納山に
ザレ場を登る。
|
 
鹿納山山頂
ドローン撮影
by N |
 
左 鹿納山山頂
右 歩いてきた尾根
遠くにダキ山
釣鐘山 |
 
左 木山内山、
桑原山、大崩山、
中和久、上和久、
七日回岩
右 鹿納山から下る |
 
左 鹿納坊主を
振り返る。
右 分岐、
ここから下る。
|
 
左 花越しに
日隠山
右 あでやか
|
 
左 隣の尾根の
アケボノツツジ
右 青空に映える。
|
 
左 美しい
右 撮らずには
おれない。
|
 
左 ずっと続く
アケボノツツジ
右 鹿納山の稜線
右端が加納坊主。
|
 
左 ミツバツツジも
鮮やか。
右 花の下を下る。
|
 
左 樅の木林へ
右 鹿納山登山口
|
 
左 荒れた林道を行く
右 日隠山登山口
伐採作業中で
林道が整備され
ここまで車が
入れる。
|
 
左 林道を下る
右 甌穴のある
谷を右下に見ながら
舗装された林道を
下る。
|
 
左 人面岩
右 ヒカゲツツジ
|
 
左 ダキ山と釣鐘山、
鹿川盆地
右 岩壁を流れる水
|
 
左 透明
右 登山口に戻る
ハードでしたが
いい山行でした。
|